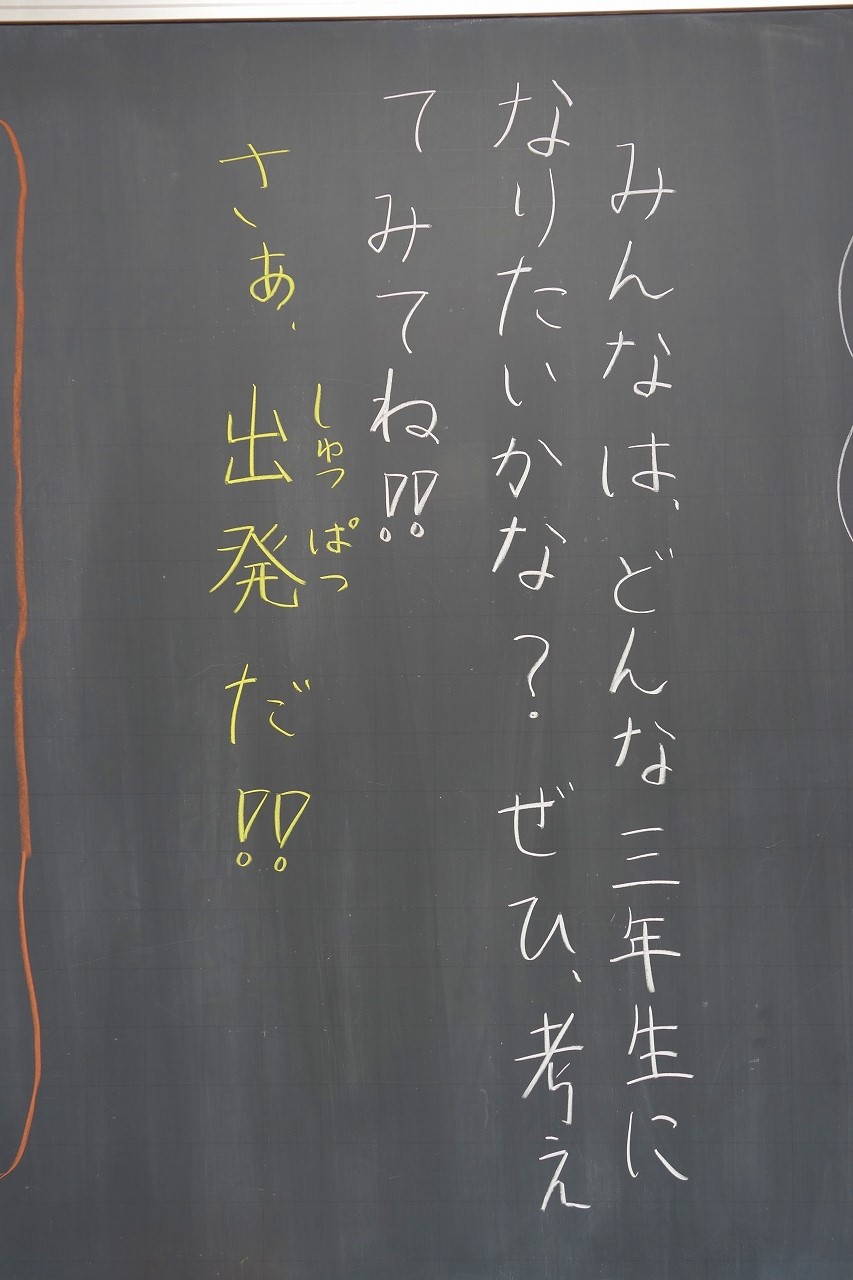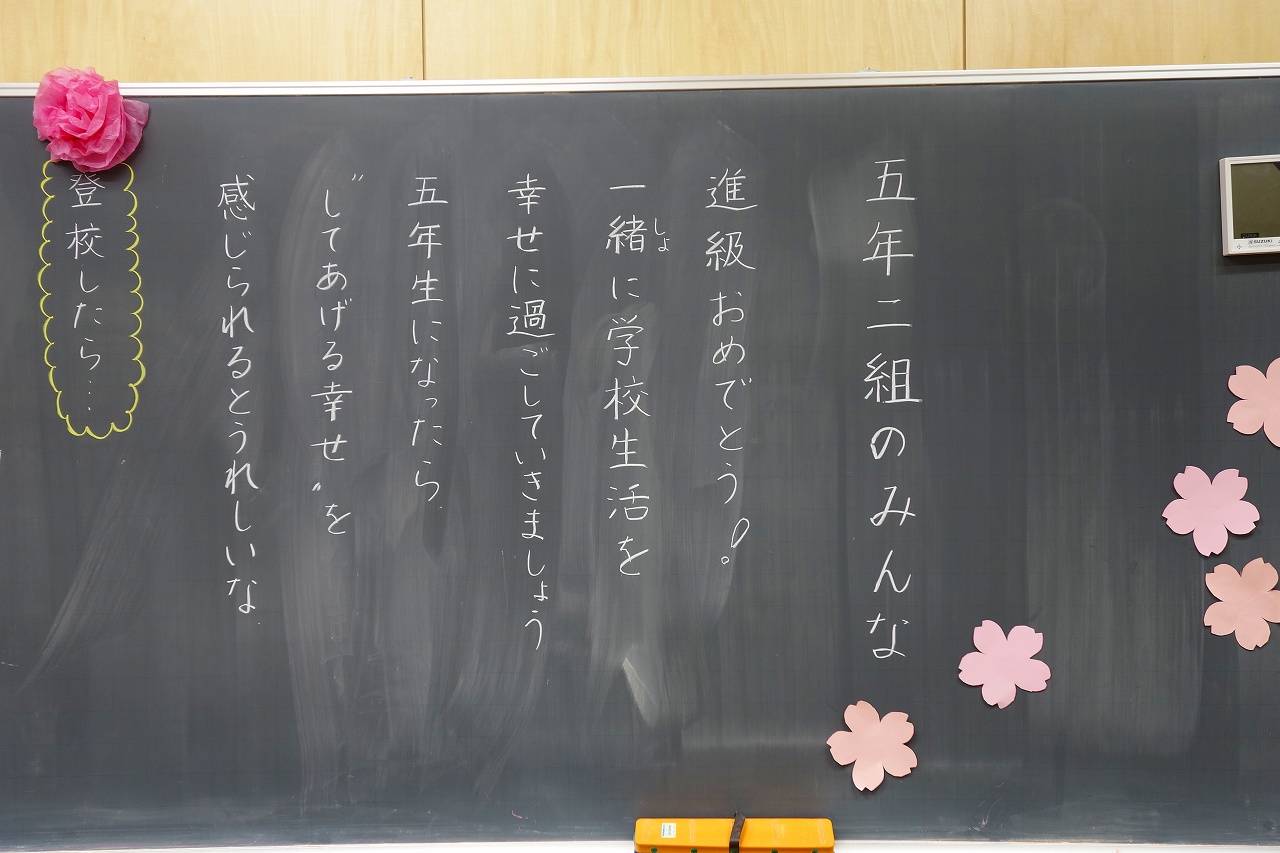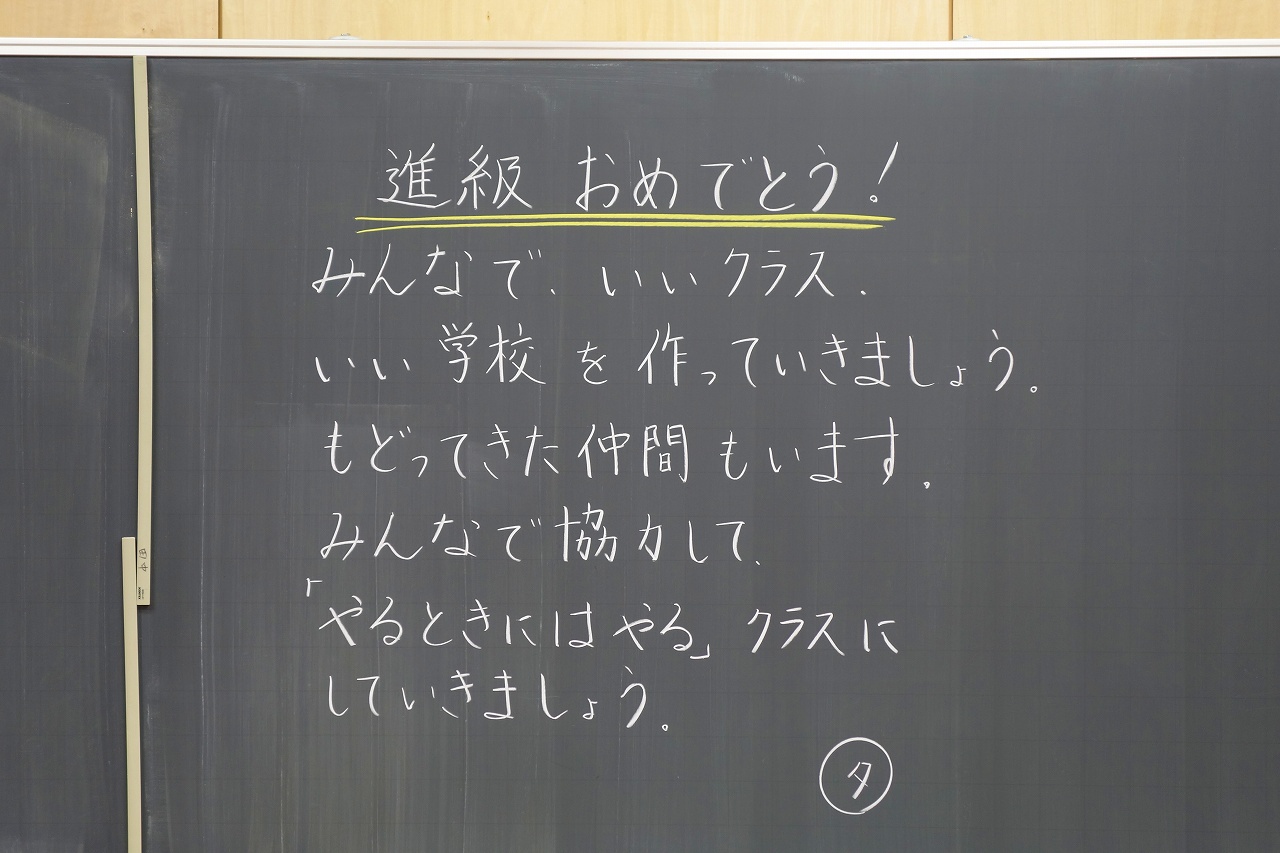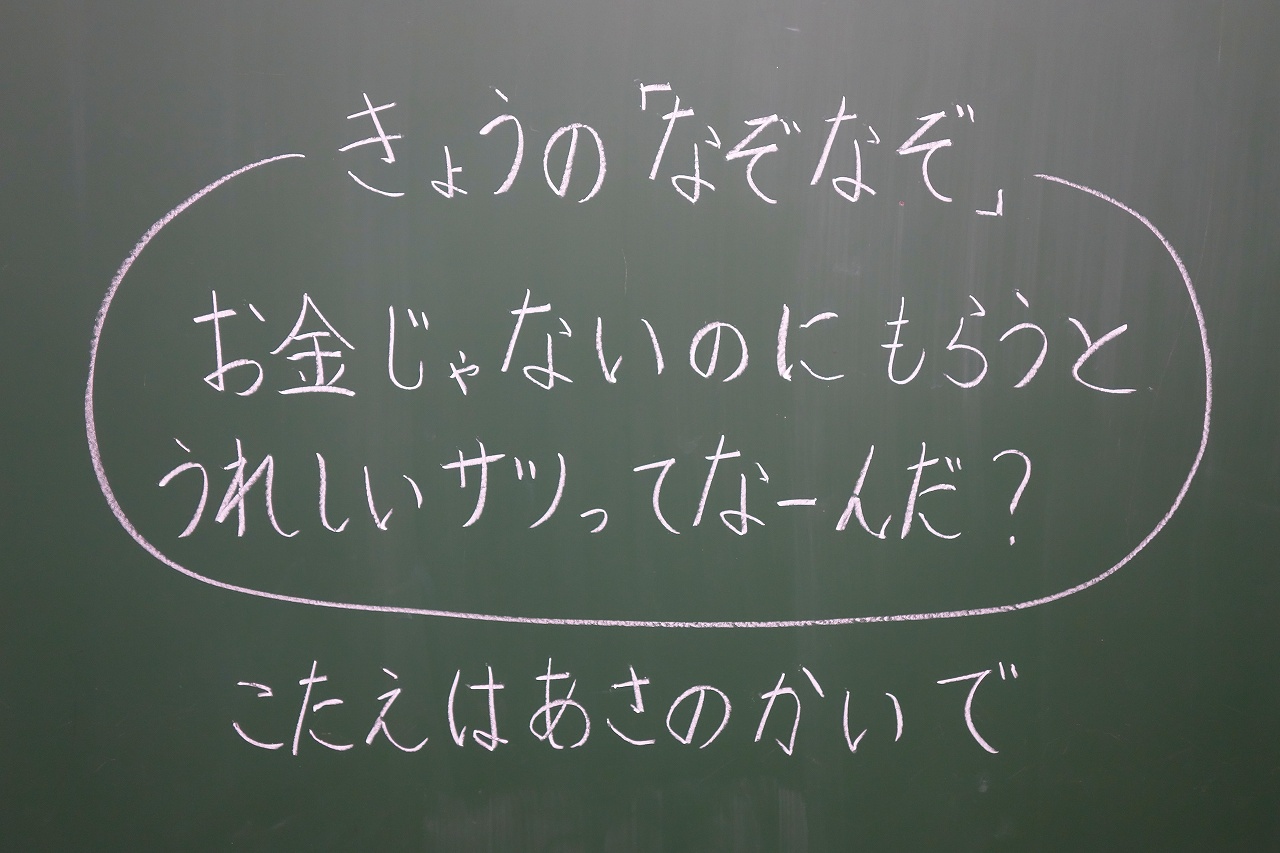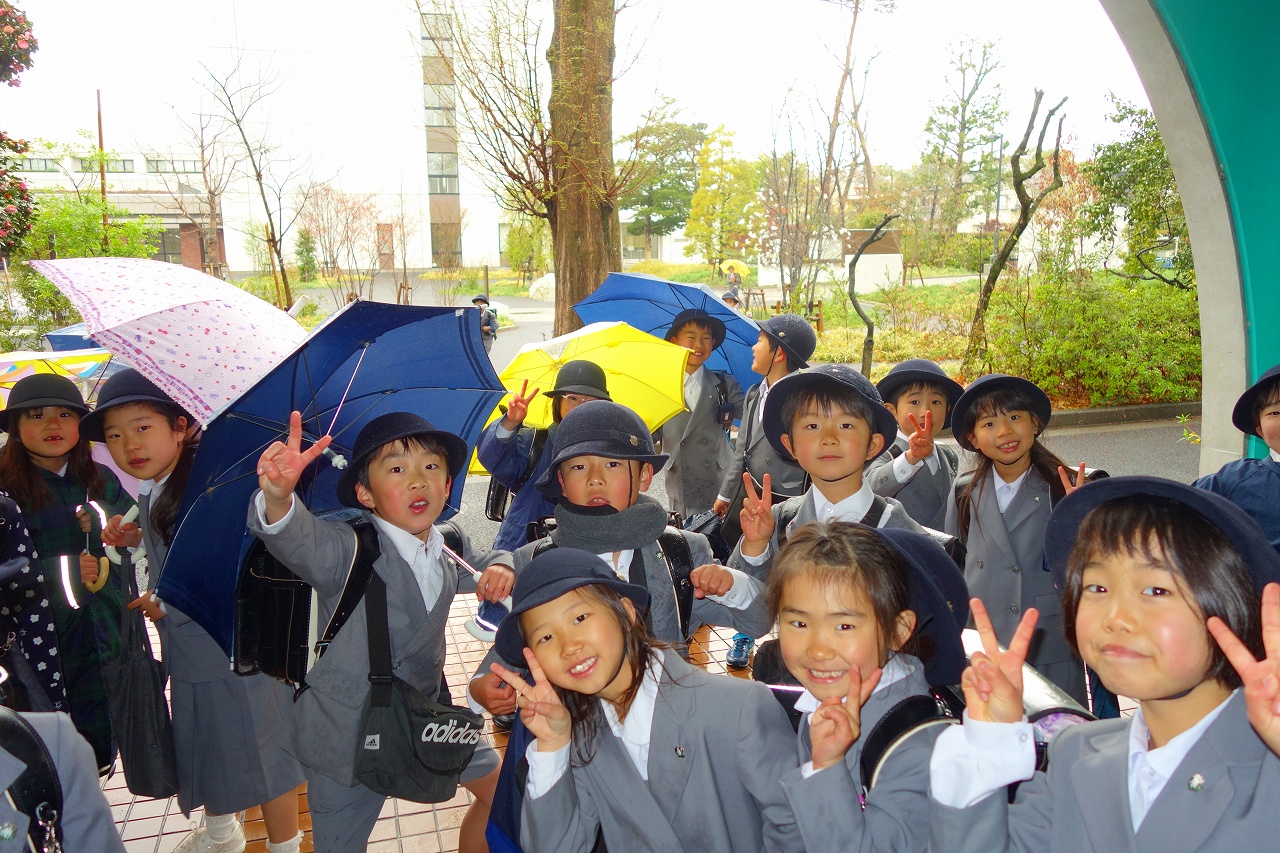2019年度の始業式の日を迎えました。
開門すると子どもたちが校舎に入ってきました。
雨の音が聞こえなくなる元気な声。
クラス替えのある学年の子どもは、玄関に張られた名簿に集まります。
「あった!」
「私は2組!」
新しいクラスにどきどきしていることでしょう。
出会いを楽しめるように手助けしていこうと思います。
元気な声に、やすらぎを覚えるなんて、なにか変な感じ。
でも学校の主役が戻ってきて、とてもうれしく、すがすがしい2019年度のスタートです。
今年度も、保護者のみなさまとともに、子どもたちの健やかな育ちを支えていこうと思います。
よろしくお願いします。